前田です。1月24日(日)は島根県松江市では1991年2月23日以来の真冬日を記録しました。外出はせず、webサーバの移行作業をして過ごしていました。
最近、webサイト全体をHTTPSで暗号化して配信する「常時SSL」を耳にすることが多くなりました。暗号化通信により傍受が防止できる、サイト利用者の安心感につながるなどののメリットがあります。
そこで、ファーエンドテクノロジーのサイト www.farend.co.jp も1月25日(月)から常時SSL化してみました。Let's Encrypt という無料の証明書発行サービスを使ったのですが、申請・取得・インストールが非常に簡単にできる仕組みが整えられていて感激しました。
ブラウザとサーバの間の通信が暗号化されるので、秘密の保護に役立ちます。通信に第三者が密かに介入して改ざんなどが行われる中間者攻撃(man-in-the-middle攻撃)も防げます。
フリーWiFiスポットなど通信傍受しやすい環境からのアクセスも安心できます。
Googleは2014年、ランキングを決定するにあたりHTTPSでの通信に対応しているかどうかを考慮するとウェブマスター向け公式ブログで発表しました。
HTTPSへの対応はコンテンツの質ほどは重視されないようですが、HTTPSに対応するだけでわずかでも点数稼ぎができるのは悪い話ではありません。
ブラウザのアドレスバーに表示される鍵マークは安全な通信を示すものとして広く広く認知されていますので、サイトの利用者の方には安心感をもってもらえます。
webサイトをHTTPSに対応させるにはサーバ証明書が必要ですが、今回の常時SSL化では Let's Encrypt で取得した無料の証明書を利用しました。
Let's Encryptは無料の証明書を提供するサービスです。運営主体はInternet Security Research Group (ISRG) という団体で、Mozilla、Akamai、Cisco、Facebookなど25の企業・団体がスポンサーとなっています。2015年12月からパブリックベータサービスが開始され、誰でも自由に利用できるようになりました。
これまでwebサイトをHTTPS対応にするための大きなハードルはサーバ証明書のライセンス料金がかかることでした。そのため、公開情報を掲示しているだけの、個人情報などを扱わないサイトでは暗号化無しで運用することが多いと思います。Let's Encryptは無料なので、例えば個人ブログサイトなどでも気軽にHTTPS化できます。
メリットは無料であることだけではありません。Let's Encryptでは証明書の取得を自動化するためのACMEプロトコルという仕組みが整備されていて、公式クライアントを使えば申請から取得までを簡単な操作で済ますことができます。Ubuntu上でApacheを使っている場合はwebサーバの設定変更も自動で完了できます。
ファーエンドテクノロジーのサイトをLet's EncryptでHTTPSに対応させた手順を紹介します。基本的には 公式サイトのドキュメント に記載されている通りで特に迷うことはありませんでした。むしろ、あまりにも簡単に常時SSL化が完了したのに驚きました。
Let's Encryptでは公式クライアントを使って証明書の申請・取得を行います。公式クライアントはほとんどのLinux環境で実行可能ですが、Ubuntu上でwebサーバとしてApacheを使っている場合はHTTPSに対応するためのサーバの設定変更まで自動で行われます。
せっかくなので、CentOS + Apacheの環境で動かしていたサイトをUbuntu + Apacheに移行しました。
細かな手順は 公式サイトのドキュメント をご覧いただくとして、ここではいかに簡単にHTTPSに対応できるのかをスクリーンショット中心に紹介します。
Ubuntu + Apacheの環境で公式クライアント letsencrypt-auto を実行すると、現在そのサーバ上で運用しているバーチャルホストの一覧が表示されます。ここでHTTPS化したいサイトを選択します。今回は www.farend.co.jp をHTTPS化するのと同時に有償のサーバ証明書で運用中の www.farend.ne.jp もLet's Encryptに切り替えるので、二つのホスト名を選択しました。

そのサーバで初めて証明書の申請をするときには連絡先のメールアドレスの入力が求められます。

メールアドレスを入力後 OK で進むと、なんと証明書の申請・承認・ダウンロードまでが即時完了します。通常だと結構手間がかかる作業なのですが、Let's Encryptだと公式クライアントを起動してから数十秒で完了してしまいました。
証明書の取得が終わるとApacheをどのように構成するか問われます。 Easy だとHTTPとHTTPSのどちらでもアクセス可能で、 Secure はHTTPのページにアクセスがあるとHTTPSのページに転送されます。HTTPS化によってページの表示に影響がないか確認してから常時SSL化したいので、まずは Easy を選びました。

"Congratulations!" と表示されました。この画面が表示された時点で、Apacheの設定も変更され HTTPS でアクセスできる状態になっています。サーバ証明書の申請とダウンロード、HTTPS化のためのApacheの設定変更がすごく簡単に完了しました。

HTTPSのページ内で暗号化されていないコンテンツが埋め込まれていると、ブラウザにブロックして表示されないことがあります。トップページを表示させて異常がないことを確認しました。アドレスバーに鍵マークが表示され、また鍵マークをクリックすると証明書の情報も表示されます。

実は一部のブログ記事は画像をHTTPで参照しているためブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されないのですが、大多数のページでは問題ないので当面は許容することとしました。
表示の確認ができたので、暗号化無しのHTTPのページへのアクセスがあった場合もHTTPSのページに転送する常時SSL化の設定を行います。letsencrypt-auto コマンドを再度実行すれば設定できます。
新規に証明書を取得したときと同じドメインを選んで、

取得済みの証明書の再インストールを指定して、

常時SSLにしたいので、今度は Easy ではなく Secure を選んで、

これでApacheの設定が更新され、常時SSL化できました。

サイト利用者の方が http://www.farend.co.jp/ しても、自動的に https://www.farend.co.jp/ に転送されるようになりました。ファーエンドテクノロジーのコーポレートサイトへのアクセスは必ず暗号化されます。
Let's Encryptを使えば無料であることだけでなく、証明書の取得・導入・更新が自動化可能な方法で行えるのが画期的だと思います。このようなサービスが提供されることで、運営するすべてのサイトを常時SSL化することが現実的になりました。ファーエンドテクノロジーでも徐々に運営サイトを常時SSL化する予定です。
無料で証明書が提供されるのはLet's Encryptだけではありません。Amazon Web Servicesも AWS Certificate Manager (ACM) というサービスを発表し、ELBおよびCloudFrontで無料でサーバ証明書が利用できるようになりました。
これらのサービスにより、HTTPS化のための大きなハードルだった証明書料金を無料にするという選択肢ができました。近い将来、規模や用途を問わずwebサイトはHTTPSで配信するのが当たり前で、暗号化無しのサイトへのアクセスは好ましくないとされる時代が到来するかもしれません。
ただ、Let's EncryptやACMで発行されるサーバ証明書はDV(証明書であり、ホスト名の管理権限のみを確認して発行される最も信頼性の低いものです。申請者が www.farend.co.jp というサーバを管理する権限があることは確認されるものの、それがファーエンドテクノロジー株式会社のサーバであることの確認は行われません。サイトの用途によっては、登記簿や電話連絡により実在する企業か審査されるOV証明書、もしくはOV証明書よりもさらに厳格な審査が行われるEV証明書を選択する必要があります。

|
オープンソースカンファレンス2026 Tokyo/Spring(2/27〜28開催)ブース出展 オープンソースカンファレンス2026 Tokyo/Spring(2/27〜28開催)にブース出展します。 |

|
My Redmine 2026 新春アップデートのお知らせ(RedMica 4.0対応) 2025年12月にMy Redmine 2026 新春アップデートを実施しました。 |
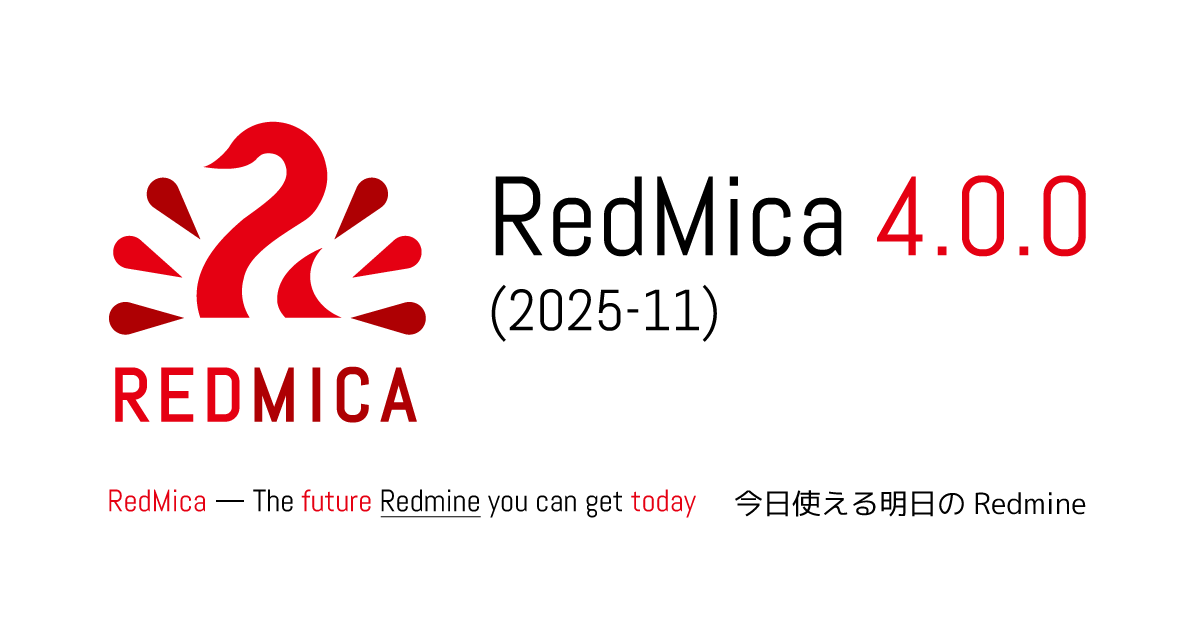
|
プロジェクト管理ツール「RedMica」バージョン 4.0.0をリリース Redmine互換のオープンソースソフトウェア 今日使える明日のRedmine「RedMica」のバージョン4.0.0をリリースしました。 |

|
Redmineの最新情報をメールでお知らせする「Redmine News」配信中 新バージョンやセキュリティ修正のリリース情報、そのほか最新情報を迅速にお届け |