前田です。オープンソースのプロジェクト運営支援ソフトウェア「Redmine」を解説した拙著『入門Redmine 第5版』が12月2日に発売されました。その5日後というタイミングでちょうどブログの順番がまわってきましたので、新しい本のことを書いてみます。
1冊の本がどんなふうにして世に出るのか、多くの方にとっては未知の話ではないでしょうか。そこで今回のブログでは、このほど発売となった『入門Redmine 第5版』がどのような過程で作られたのか紹介してみます。
本を出版するには、まずは出版社で企画を承認していただく必要があります。
1点の本を世に出すには、制作(編集・レイアウト・印刷など)、流通、販促に多額の費用(おそらく数百万円以上)がかかります。本が売れなければ費用が回収できず赤字になってしまいますから、一定の売上が見込めないと承認されません。
「入門Redmine 第5版」の場合、初めて本を出したときからずっとお世話になっている秀和システムの編集担当の方に、昨年末に第5版の打診をしました。

企画化してもらうには、まずは目次案を作ります。これをインプットに、出版社の編集担当の方が社内用の企画書を作ります。執筆はこの目次案をもとに進めるので、本の骨格が決まる重要な作業です。

目次案は1人で作るのではなく、編集担当の方からのアドバイスもいただきます。第5版でいただいた提案の1つが、ストーリー仕立てでRedmineの使い方を学べる章を入れるというものです。Redmineが初めての方にもなんとなく雰囲気を理解してもらうためです。上に載せた画像では「ストーリーで学ぶRedmineの使い方」となっていますが、これが最終的には「Chapter 1 バーベキューの段取りでRedmineを体験してみよう」になりました。
2016年2月16日に最終の目次案が確定し、23日に企画承認のご連絡をいただきました。

本が出ることが決まったら、あとは脱稿に向けてコツコツ書き続けます。
今回は、12月初旬発売に向けて9月20日脱稿というスケジュールが設定されました。企画承認が2月なので、約7ヶ月の期間です。微修正にとどまらず全面的な見直しをしたかったので、長めの執筆期間をいただきました。

約半年間の間、原稿を書き続けるのは私にとっては結構大変な仕事です。これまでの経験を振り返ると、書き続けるために最も大事なことは毎日書くということです。
書かない日が数日続くと、再開するのにだんだん気持ちのハードルが高くなる気がします。ようやく取りかかっても、頭の中から本のことがかなり消えていて、前に考えていたことを思い出すのに苦労します。1行だけでもよいので日々原稿をさわるようしていれば、執筆が習慣になってきますし、頭の中から本のことが消えていってしまうのも防げます。
第5版では毎日書けたかというとそうでもないのですが、それでもなるべく日にちを空けないように注意していました。

執筆中は編集担当と頻繁に連絡や相談を行います。第5版ではコミュニケーションとのツールとしてチャットツールの「Slack」を利用しました。小さなコミュニケーションが素早くできて非常に便利でした。
例えば、前田の泣き言に対して…

いただいたアドバイス。

このようにコミュニケーションを密に行いながら、一緒に執筆を進めます。
アプリケーションソフトの解説書には、スクリーンショットが多数掲載されていることが多いです。入門Redmineも例外ではなく、400点以上掲載されています。スクリーンショットを撮るのは、それらしい画面を準備するのに手間がかかり、案外大変です。
スクリーンショットの多くは、単純に画面をキャプチャしただけではなく文字や囲みを加えたものもあります。私の場合、それらの図はIllustratorを使って作りました。原寸で作成したので、ほとんどのデータを無加工でそのまま紙面で使っていただきました。
ただ、単にスクリーンショットを撮るだけでも手間なのですが、Illustratorで小ぎれいに作っていたのでさらに時間がかかってしまいました。


ちなみに、Illustratorを使う著者はあまりいなくて、PowerPointで画像の上に囲みや文字を加えたデータで納品されることが多いそうです。その場合、出版社のレイアウト担当の方がPowerPointから画像や文字をコピーしてIllustratorデータを作る必要があります。
原稿を出版社に納品した後、実際に紙に印刷するためのレイアウトが行われ、その後著者による校正が行われます。入門Redmine 第5版の場合、10月下旬から11月上旬にかけて計2回の校正を行いました。
「校正」といえば、一般的には単純な誤字・脱字のチェックを言いますが、私の場合は「推敲」の範囲の作業も含んでいるので、この段階でも原稿をかなり変更します。本来は執筆の段階で十分推敲を重ねるべきなのですが、時間が足りなかったりレイアウトされたものを見て気がつくことがあったりして、校正の時点でも相当手を入れてしまいます。
そのため、校正も私にとっては執筆と同じくらいに大変な仕事です。むしろ、使える時間が短い分、より大変な気もします。それでも、これまでは1人でやっていたのですが、今回は社員に手伝ってもらったので、効率的に品質を高めることができたと思います。

校正内容の指示は、Adobe ReaderでPDFに注釈を追加することで行います。校正済みのファイルはDropboxで共有しました。

そして11月15日、私の校正作業と出版社での校正内容の反映が終わりました。長い執筆期間が終わり、あとは発売を待つだけです。

アナウンスされている発売日は12月2日ですが、本の流通はいろいろ複雑なようで、ある日に一斉に店頭に並ぶのではなくその前後から順次販売が始まるようです。11月末から大型書店で並び始めました。
執筆は大変なのですが、本が出来上がって店頭に並ぶとそんなことも忘れてしまいそうになります。
お知らせ:秀和システム『入門Redmine 第5版』の著者、前田剛さんより直筆POPをいただきました。ぜひ店頭でご覧ください。 pic.twitter.com/nZwKqzuqFM
— ジュンク堂書店池袋本店/PC書 (@junkudo_ike_pc) November 28, 2016
8年前の6月、初めて執筆の打診をいただいたときにはこんなことを言っていました。
書籍の執筆依頼が来た。こんな機会は次もあるとは思えないので、受けるつもり。
— MAEDA, Go (@g_maeda) June 19, 2008
8年後、その本の第5版を出させていただけるとは本当にありがたいことです。版を重ねることができるのは、Redmineの開発者や利用者の方々のおかげでRedmineがまだまだ広がりつつあるのが一番大きな理由だと思います。
第6版も出すことができるよう、Redmineのさらなる普及のために、できることにしっかり取り組んでいきたいと思います。

|
オープンソースカンファレンス2026 Tokyo/Spring(2/27〜28開催)ブース出展 オープンソースカンファレンス2026 Tokyo/Spring(2/27〜28開催)にブース出展します。 |

|
My Redmine 2026 新春アップデートのお知らせ(RedMica 4.0対応) 2025年12月にMy Redmine 2026 新春アップデートを実施しました。 |
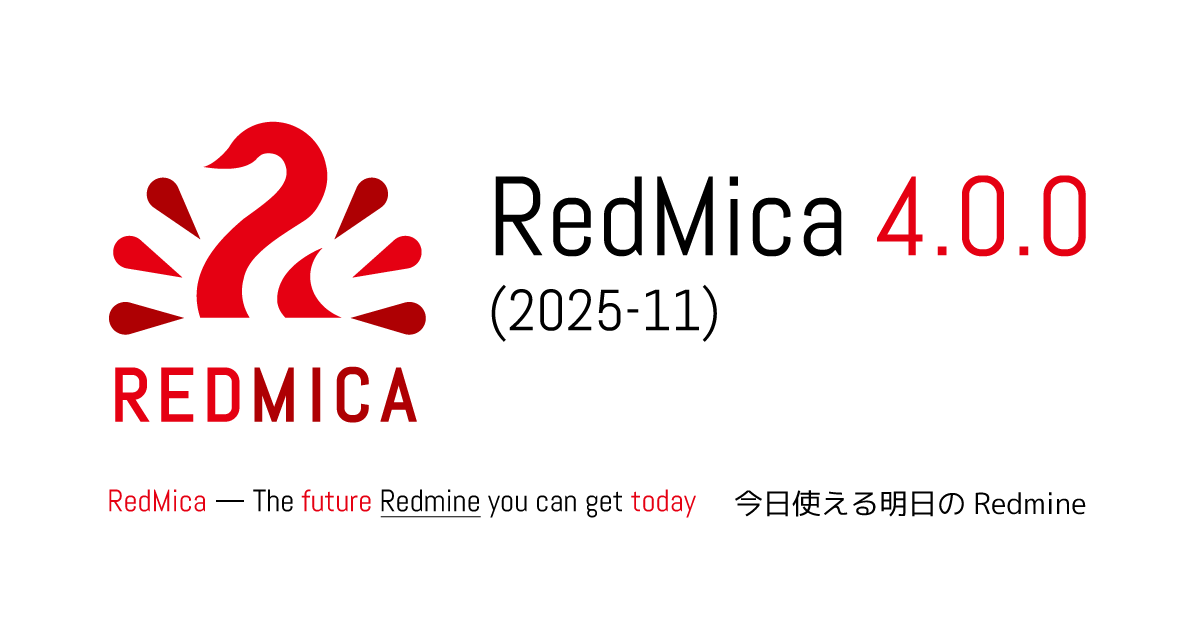
|
プロジェクト管理ツール「RedMica」バージョン 4.0.0をリリース Redmine互換のオープンソースソフトウェア 今日使える明日のRedmine「RedMica」のバージョン4.0.0をリリースしました。 |

|
Redmineの最新情報をメールでお知らせする「Redmine News」配信中 新バージョンやセキュリティ修正のリリース情報、そのほか最新情報を迅速にお届け |