3行で言うと…
吉岡です。四国クラウドお遍路 2024 in 高知の中で参加した「AWS生成AI ハンズオン」でAWSの生成AIに触れ、その可能性に興味を持ちました。 この体験をきっかけに、業務への活用を検討しつつ、再度、公式のAWS生成AIワークショップを試してみました。
本ブログでは、ワークショップの体験や得られた知見を共有し、生成AI導入を検討する方への参考情報を提供します。
AWS生成AIワークショップは、AWS上で生成AIを活用したアプリケーションの構築を体験できます。 社内データを活用したチャットボットや文章校正、画像生成などの具体的なユースケースを通じて、Amazon Bedrock(Generative AI)やCDKの使い方を学べます。 生成AIを業務に取り入れるための実践的な知識とスキルを、短時間で効率よく習得できる内容となっています。
ワークショップは、提供された手順書に沿って進めるだけでスムーズに構築が進められる設計でした。 今回は、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を利用して、ナレッジベース型の生成AIアプリケーションを構築しました。 データソースには、弊社のサービス紹介サイト「My Redmine」を使用しました。
デプロイ作業
手順書通りに進めることで、特に詰まることなくデプロイを完了。Amazon BedrockをはじめとするAWSサービスの直感的な設計が、初心者にも扱いやすいと感じました。
質問と応答の確認
実際に以下の質問を行い、生成された回答の正確性を確認しました。
簡潔に聞いてみましたが、プランごとの料金やストレージ容量を的確に回答されて、顧客向けとしても十分に使用できるレベルでした。
実際に問い合わせにありそうな難しそうな質問をしてみましたが、サービス提供者と顧客それぞれの責任範囲を明確に説明しており、こちらも問い合わせ対応としても優れた内容でした。
注意)検証環境につき、質問に対する回答はサービスの仕様とは異なる可能性がありますのでご注意ください。
このワークショップでは、RAGを活用することで、実務に直結した生成AIアプリケーションを短期間で構築できることを実感しました。 特に、ナレッジベースを利用した情報提供や問い合わせ対応の自動化に大きな可能性を感じました。
AWS生成AIワークショップを通じて、生成AIの活用可能性と注意点について多くの知見を得ることができました。
RAGの更新が容易でメンテナンスコストを低減
データソースの更新が簡単で、たとえばサービス紹介サイトを更新する際にRAGも併せてアップデート可能。情報の一貫性を保ちながらメンテナンスコストを削減できます。
サポート業務の効率化
カスタマーサポートにおける情報検索や回答作成を効率化。問い合わせ対応の迅速化と正確性向上が期待できます。
コストの考慮
Kendraなどを統合した場合、月々数万円程度のコストが発生します。導入の際には、費用対効果を慎重に評価する必要があります。
ハルシネーション対策
正確性が求められる業務では、内部利用(FAQなど)と外部利用(顧客対応)を分けることでリスクを軽減できそうです。
AWS生成AIワークショップを通じて、生成AIの実務での活用方法や可能性を具体的に学ぶことができました。 特に、RAGを使ったナレッジベースの構築や、AWSツールを活用した効率的な開発の重要性を実感しました。
生成AIは、カスタマーサポートの効率化や社内ナレッジの共有、新しいサービスの開発など、幅広い分野で大きな可能性を秘めています。 AWSは、その導入を支える強力な基盤を提供しており、今後さらに進化していくことで、生成AIの活用範囲はますます広がるでしょう。
このブログが、生成AIの導入を検討している方々にとって、参考になる内容であれば嬉しいです。 AWS生成AIワークショップで得た知見を活かし、業務での成果を出すためにこれからも挑戦していきたいと思います!
【スタッフ募集中】
弊社ではAWSを活用したソリューションの企画・設計・構築・運用や、Ruby on Rails・JavaScriptフレームワークなどを使用したアプリケーション開発を行うスタッフを募集しています。採用情報の詳細
弊社での勤務に関心をお持ちの方は、知り合いの弊社社員・関係者を通じてご連絡ください。
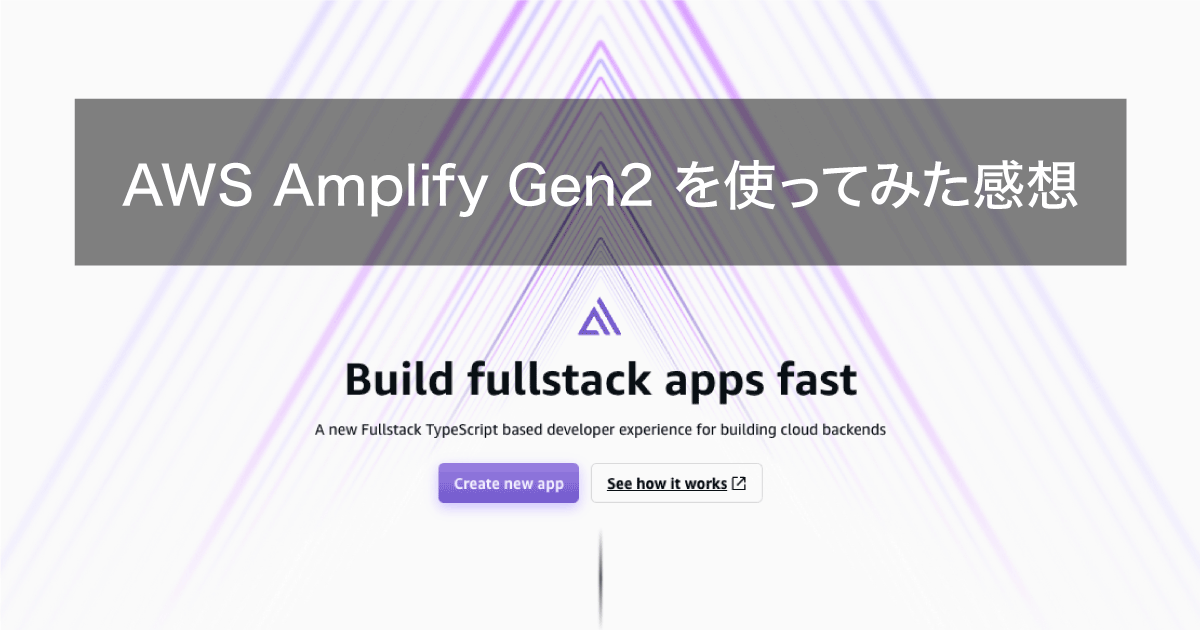
|
Amplify Gen2の検証で、サンドボックス機能とCDKが開発効率とデプロイの安定性を向上させ、AWSとCDKの知識が重要と確認されました。 |
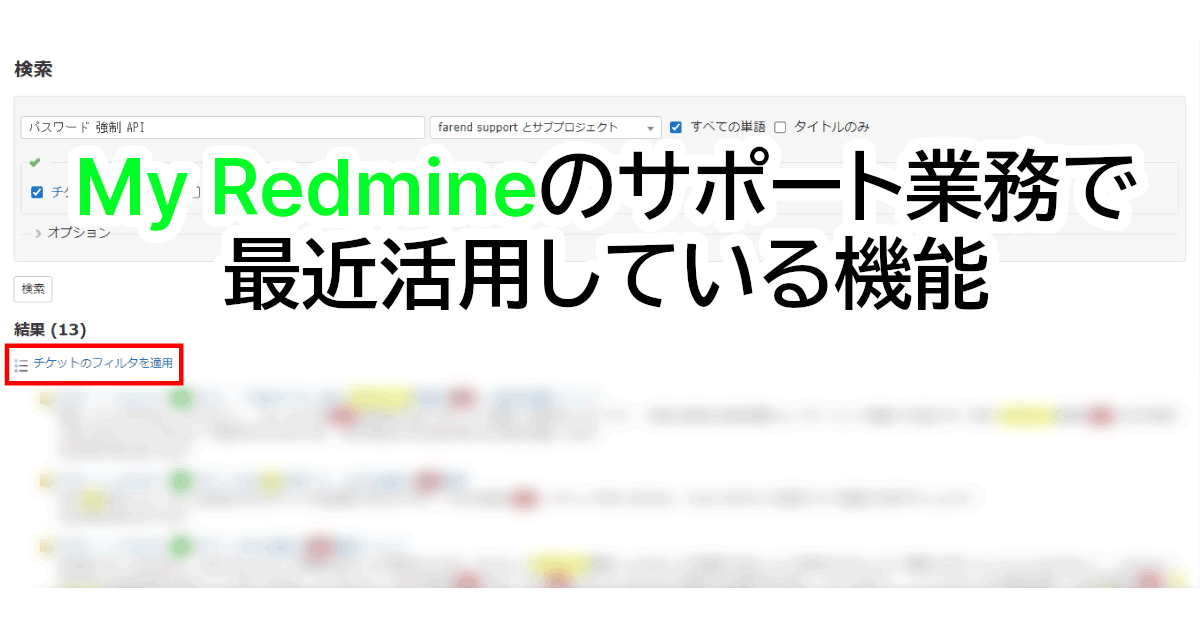
|
お客様からのお問い合わせ対応にRedmineを使っています。 |
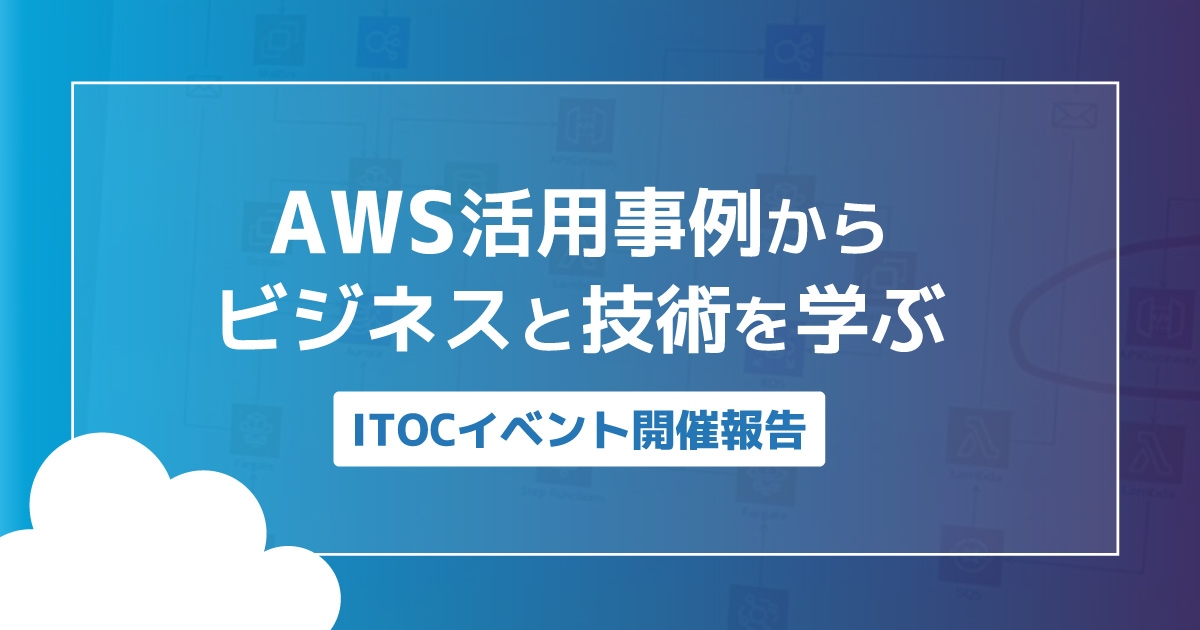
|
しまねソフト研究開発センター(ITOC)様のイベントに企画から関わらせていただきました。 |
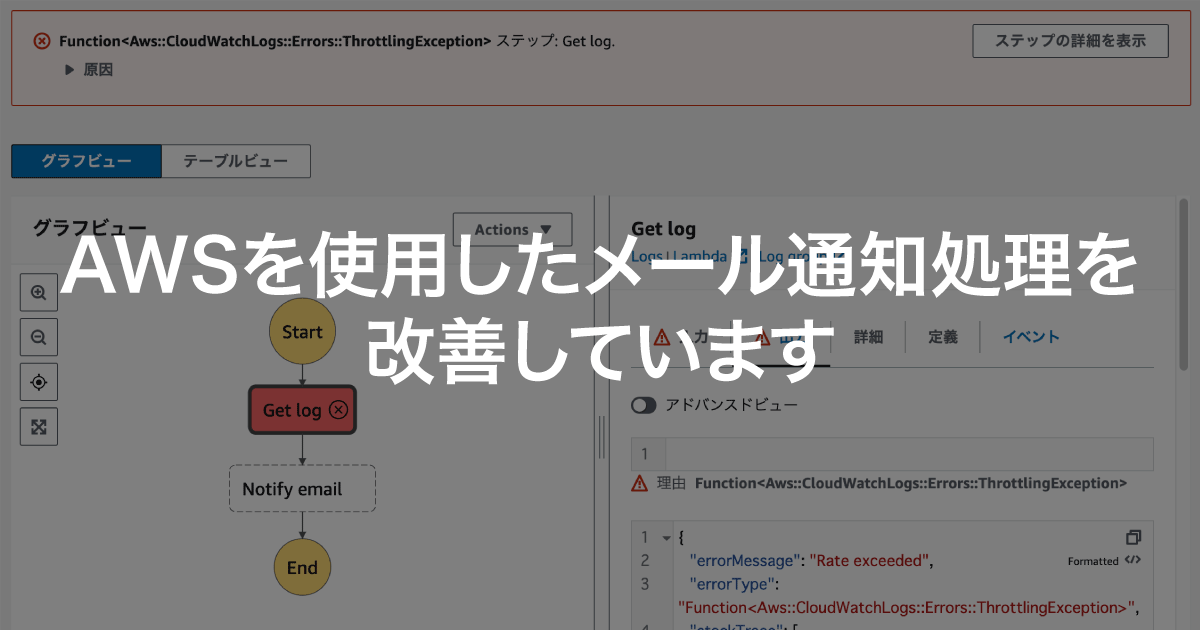
|
AWSを使用したメール通知処理を行っています。 |

|
AWSの使用コスト削減に有効なSavings Plansについて、試行錯誤して完全に理解できました。 |
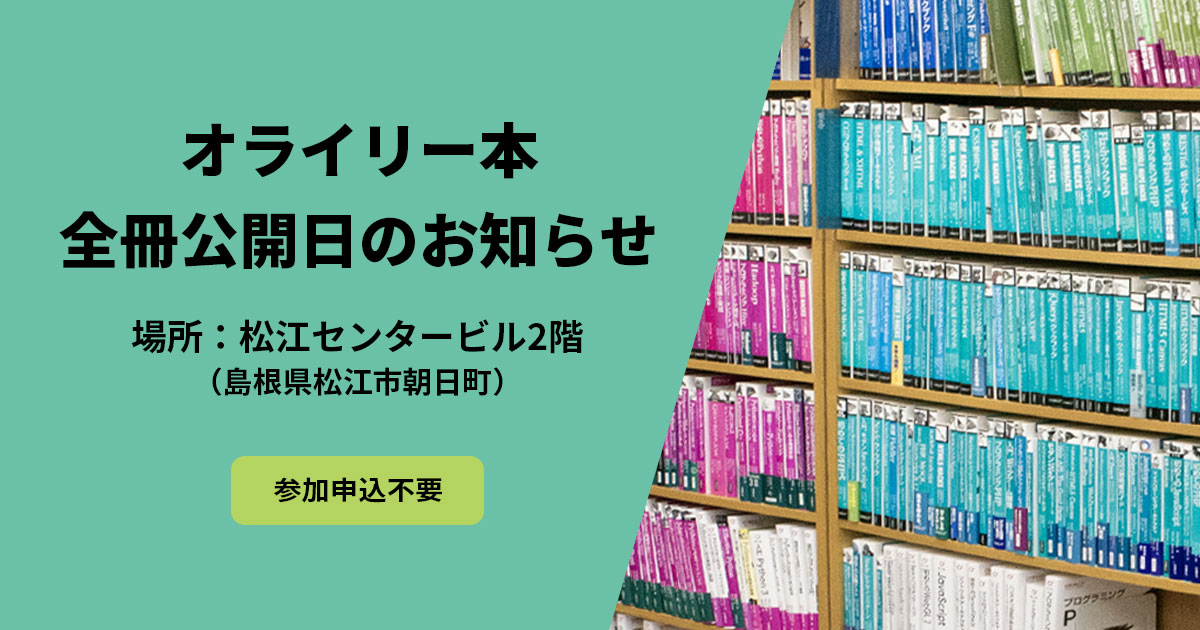
|
2025年7月6日 オライリー本の全冊公開日のお知らせ(もくもく勉強会も同時開催) ファーエンドテクノロジーが所蔵するオライリー本(全冊)公開日のご案内です。公開日には「もくもく勉強会」も同時開催します。 |

|
JANOG56ミーティング(7/30〜8/1開催)にRubyスポンサーとして協賛・ブース出展 JANOG56ミーティング(7/30〜8/1開催)にRubyスポンサーとして協賛、ブースを出展します。 |
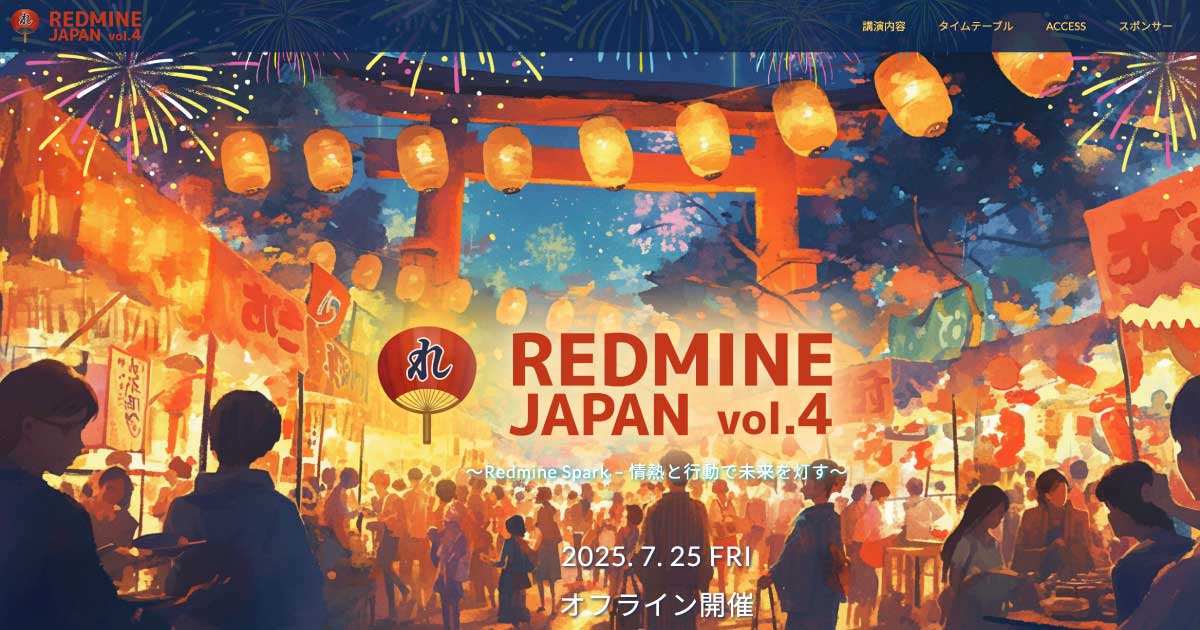
|
Redmine Japan Vol.4(7/25開催)に弊社代表の前田が招待講演として登壇 オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア Redmine のイベント「Redmine Japan Vol.4」に弊社代表でRedmineコミッターの前田剛が招待公演に登壇します。 |

|
RedMica 3.2 バージョンアップのお知らせ My Redmineで提供しているソフトウェアをRedMica(ファーエンドテクノロジー版Redmine) 3.1 から 3.2 へバージョンアップいたします。 |

|
Redmineの最新情報をメールでお知らせする「Redmine News」配信中 新バージョンやセキュリティ修正のリリース情報、そのほか最新情報を迅速にお届け |

